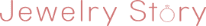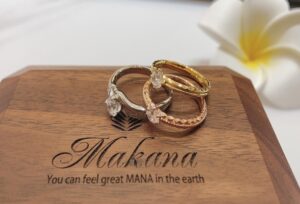福井市エルパ時計の寿命ってどれくらい?

時計の寿命ってどれくらい?
日常でもビジネスシーンでも欠かせない時計。永くお使いいただくものだからこそ、いつまで使えるのか気になりますよね。また新しく腕時計を買うときにも時計の寿命は気になりますよん。今回は時計の種類別に解説していこうと思います。まず、前提として時計はいくつか種類に分けられることはご存知でしょうか。クォーツ式、機械式、ソーラー式の3種類に分けられます。それぞれ使い勝手もメンテナンスも大きく全く異なります。今回はクォーツ式、機械式、ソーラー式のそれぞれがどのような特徴を持っているのかと長く使えるコツもお伝えします!
目次
クォーツ式とは?

こちらは電池で動く時計です。皆様に一番馴染みが近く、使っている方も多いと思います。クォーツとは水晶の事で、水晶の持つ電圧をかけると正確に振動する性質を腕時計の仕組みに利用しているもの。この水晶の性質は1880年にフランスの物理学者によって発見され、1927年にはアメリカの研究者たちによりクォーツ時計の施策が始まりました。しかし実用化には至りるまでにはいたりませんでした。1937年になると日本で古賀逸策が日本初のクォーツ時計を開発したと言われています。この機構を腕時計に組み込んだのが日本を代表する時計ブランドのセイコー。ここで世界初のクォーツ式腕時計が誕生します。セイコーが特許を権利化したうえで機構を公開したことにより、世界中でクォーツ時計が作られるようになりました。それまで使われていた機械式時計よりも正確で安価なクォーツ時計。クォーツ式の時計は瞬く間に急速に世界中に広まりました。電池が持つのが2~3年なので定期的な電池交換が必要となりますが、コストパフォーマンスが高いものが多いクォーツ時計。また機械式時計と比べると、使用しているパーツが少ないため衝撃にも強いのが特徴です。しかし、強いからと言っても扱い方によっては時計の寿命を縮める原因にもなるので注意が必要。クォーツ時計の注意点として、電池の液漏れにより時計の内部が腐食するという点があります。これは、電池がなくなったのにもかかわらず放置しておくとよく起こってしまう現象。電池がなくなった際は早めの電池交換をするのがおすすめ。使わないのであれば電池を抜くことを頭においておくと良いですよ。
機械式時計とは?

こちらはゼンマイを動力源に動く時計。巻きあがったゼンマイがほどけようとする力により動くという仕組みです。しかし、ゼンマイの力をそのまま針に伝えると、猛スピードで針が回転してしまうため、てんぷという部分の正確な振動によって歯車を調整しながら針を動かしているという複雑なもの。クォーツと比べるとたくさんのパーツを使っており、厚みと重みがあるのが特徴です。その為、衝撃を受けると壊れてしまう可能性がどうしても高くなってしまう性質が。世界で初めて作られた機械式時計は、1300年頃の北イタリアから南ドイツまでの地域で作られたと言われています。一日に時間が大きくずれるというのは機械式時計の特徴。当時の時計としての精度は1日に50秒ほどズレたと言われています。現在の時計がいかに進化し、優れた精度を持っているのかが分かりますね。1970年代になると値段も低く、精度も高いクォーツ時計が発表されました。これにより機械式時計は大きな打撃を受けます。この出来事はクォーツショックと呼ばれています。クォーツショックにより低迷していた機械式時計ですが、1990年代ごろから再び注目を浴びるようになります。機械式時計は高い技術力をもつ職人たちによって手作業で作られているため、クォーツ時計とはまた違った手作りならではの魅力が再認識されました。また、機械式時計の良さは、メンテナンスをしていれば数10年使い続けること。親から子に、そして孫に、永く世代を超えて使っていけます。きちんととメンテナンスをしながら丁寧に扱っていれば半永久的に使えることが出来るのです。 100年以上前に作られた時計をアンティーク時計と言い、実際に愛用している方も多くいます。
ソーラー式時計とは?

こちらは太陽光で充電して動く時計になります。ダイヤル面に受けた光を二次電池に充電蓄積をし、電力を電気に変換することで動力エネルギーとし動いています。二次電池とは、生活の中でよく使う乾電池のような使い捨てのものとは異なり、充電と放電を繰り返して使えるもの。二次電池は環境に配慮した電池と言われています。クォーツ時計のように2~3年に一度の電池交換をしなくて良いため、手間もお金もかかりません。しかし、長年使用しているとスマートフォンのバッテリーの様に劣化し、最大限まで充電してもすぐに止まってしまうということが起こります。そうした場合は二次電池交換のタイミングの合図。二次電池を交換することによってまたお使いいただけます。また、ソーラー時計の中には電波付きソーラー時計という時計があります。通常の時計はリュウズで手動で時間を合わせますが、こちらは時計が電波を受信して時間を自分で操作しなくても合わせてくれる時計です。機械式時計の様に手間がかかる時計を面倒と感じる人や、正確さを求める人には特にオススメ。しかし、通常のクォーツ時計と比べるとお時計自体が少し高価になる傾向が。ソーラー時計が世界で初めて発表されたのはラゲーンセミコンダクター社のシンクローナ2100で1972年にまで遡ります。世界初のソーラー時計はソーラーセルを搭載したLEDウォッチとして誕生したと言われています。1976年にはアナログ式光発電時計をシチズンが発表し、翌年の1977年にはセイコーがソーラー発電時計を発表しました。当時は最新の技術だったため非常に高価ではありましたが、1990年以降は光エネルギーから電力への変換効率の向上や、ソーラー式のシンプルな機構により広まっていきました。
時計ってどのくらい持つ?

時計の種類は分かったけど、時計は全部寿命は同じなのか、全く変わってくるのか気になりますよね。電池の時計であれば電池交換をすればずっと使えるのでしょうか?次はそれぞれの時計がどのくらい使えるのか考えていきましょう!
クォーツ式時計の寿命

クォーツ時計は定期的に電池を交換することで長く使うことができます。しかし、内部の電子回路には寿命があり、10年~30年程度と言われています。もちろん時計によって個体差があるため、10年よりも先に動かなくなってしまうものも、何十年使えるものもあります。電子回路の劣化により故障した場合でも、交換できる部品さえあれば修理が可能。しかし、その時計専用の電子回路の部品が必要となるため、メーカーが生産を終了しており在庫がない場合にはそこで寿命が来てしまいます。クォーツ時計を長く使いたい場合は限定や新しいものではなく、ロングセラーのものを選ぶと良いかもしれませんね。クォーツ時計の寿命を縮めてしまう原因の中で多いのが、電池の液漏れによる部品の腐食です。なぜ液漏れが起きるのかはご存知でしょうか?電池が切れて時計が止まっている状態で放置しておくことが一番大きな原因。多くの人が止まったまま放置し、使いたいときに電池交換することが多いですが、頻繁なチェックがオススメ。あまり出番のない時計でも長くつかうためには定期的に止まっていないかをチェックしたり、止まっているけれどしばらく使わないというようなときには電池を抜くことがポイント。
機械式時計の寿命

機械式時計は一生ものとよく耳にするかと思いますが、それは本当なのでしょうか?機械式の場合は何世代にもわたり受け継いでいく時計になるほど長くお使いいただけるケースと、数年で寿命が来てしまうケースがあります。結論から言うと多くの場合は持ち主の使い方と時計によります。長く使用するためにはどのようなことが重要となってくるのでしょうか?最も日々気を付けることが出来て、時計にも重要なことは丁寧に扱い使うこと。機械式時計は先ほどご紹介させて頂いた通り多くの部品を使用しているのが特徴。乱雑に扱うとその分時計は傷み、不具合が起きて、交換しなければならない部品も増えてしまいます。内部の部品の交換はほとんど代替品での交換が可能ですが、文字盤や外装、針などの修理は元々の時計本来の雰囲気がなくなってしまうことも。また、長い間使わずに置いておくことも時計に良くないのですが、毎日動かし続けることも時計の劣化を早める原因になります。もちろん毎日使うなら素晴らしいことですが、使わないのに動かしているとただ部品の摩耗を早めてしまうことにもなります。時計をいくつか持っている人は、数日おきに他の時計と使いまわすと部品の摩耗が軽減し、より長くお使いいただけます。また、オーバーホールと言われる定期的なメンテナンスも長く使用する上で重要なポイントに。
ソーラー時計の寿命

ソーラー時計は二次電池に蓄電をするため定期的な電池交換は不要ですが、二次電池が劣化しないわけではありません。長期的な使用や使用環境によって電気エネルギーを蓄電する二次電池の容量や充電効率が低下していきます。わかりやすい例で言うとスマートフォンのバッテリーのようなイメージ。スマートフォンも長く使用していると、フル充電をしても持ちが悪くなったり、新品の状態で100%充電できていても2〜3年経つと、80%程しか最大でも充電されなくなったりしますよね。ソーラー時計も同じで、充電の持ちが悪くなり、充電をしっかりとしているのにすぐに止まってしまうということが起こります。このソーラーの二次電池の劣化が始まる時期が大体7年ほどと言われています。劣化が始まるだけですぐに使えなくなるというわけではないため、寿命で言うと大体7〜10年前後は使えるケースが多いです。二次電池が劣化してしまい使えなくなった場合は、二次電池を交換することによってまた使うことができます。ソーラー時計と長く使うために大切なことは、定期的に光を当てて止まらないようにすることです。ソーラーに二次電池は充電を絶やさず時計が止まらないようにしておけば10〜15年の使用も見込めます。しかし、引き出しにのような暗所にしまい込んでいると充電不足で止まってしまい、二次電池の劣化を進める原因になることも。また、一度、充電がなくなって止まってしまうとフルまで充電するまでに時間もかかるため、時計が止まらないような使い方をすると良いです。夏場は太陽光も強く、充電するという意識がなくても勝手に充電されるためあまり心配はいりませんが、冬場は注意が必要。天気が悪い地域では太陽光が出にくく充電がされにくいのです。また長袖で時計の文字盤が隠れてしまうケースも。着けて使ってさえいれば勝手に充電されると思いがちですが、冬場は長袖に時計が隠れて太陽光が当たらないため、使っていたのに止まってしまったと言うケースが起こりやすくなります。使用しない場合でも月に一度、天気の良い日に4〜5時間太陽光で充電すると止まる心配なく使えます。ソーラーは太陽光で充電をして止まらないようにすることが目安。室内光でも全く充電されないわけではないですが、太陽光の方が早く確実に充電することが出来ます。
オーバーホールとは?

オーバーホールとは簡単に言うと時計を分解して行う大規模な時計の掃除のこと。これはクォーツや機械式、ソーラーに限らず行います定期的に行うことにより、時計の寿命を伸ばしたり、精度を回復させることができます。オーバーホールは定期メンテナンスと言われるように、故障する前に行う点検作業になります。故障する前に行うことで故障を防ぎ、もし故障した際でも部品が摩耗などで劣化して交換になり、修理料金が高額になることを防いでくれます。オーバーホールの目的は、時計の機能が正常に働いているかの確認、そしてその機能を継続して果たせるようにすることです。オーバーホールは時計の内部をバラバラに分解して、日常的ではできないような細かい部分まで点検を行います。そのため頻繁には行いませんが、コストも金額も掛かってきます。
オーバーホールの実施期間

時計に部品には、部品同士が接触する際に摩耗しないようオイルが塗ってあります。このオイルには使用期限があり、オイルが切れて乾燥した状態で時計を使用すると、部品同士が擦れ合い摩耗して不具合が起きてしまいます。摩耗がひどい場合には部品交換が必要になることも。また、そのオイルの汚れにより時計に不具合が起きることも。オイルの使用期限は5〜6年と言われているため、定期的なメンテナンスでオーバーホールをする方はこの時期にする方が多いのではないでしょうか。よく使っていなかったから…と言われる方がいますが、時計を使用していない間もオイルは乾燥を始めています。特に油汚れが付いたまま放置している場合だと、油汚れが固着してしまっている場合も。クォーツ時計は通常電気交換は2〜3年に一度ですが、それよりも早いと油汚が原因になっている可能性もあります。汚れにより消費電力が増えて、電池を入れても直ぐに止まってしまうのです。
オーバーホールの流れ

①分解
始めに時計を分解します。中の部品を細かく分解することで、日常的に行うメンテナンスでは見られない時計の内部の部分を確認することができます。
②点検
先ほど分解した部品が劣化していないか、摩耗していないか、これからも使えるかの確認をします。部品が激しい摩耗や修復不可能な損傷がある場合は部品の交換となります。この点検の際に必要な部品の発注となるのですが、在庫がなかった場合は納期が延びる原因となります。
③洗浄
部品や機器内部の洗浄をして汚れを落とします。特に何年もオーバーホールを行われていない時計は汚れの蓄積で落ちにくいため、専用のブラシや洗浄液が使われます。錆や汚れが酷い部品は洗浄をしてから点検を行う場合もあります。
④修理と交換
摩耗や劣化が激しい部品は交換、洗浄後に加工が必要な部品は修理されます。修理内容は設備の用途により変わりますが、研磨や肉盛りなどを行い性能を高めます。
⑤注油
オイルを差すことにより、部品の摩耗を防ぎます。摩耗による損傷や錆を防ぐことができるため、回転やスライドする部品の寿命を延ばすことができます。
⑥組み立て
全ての部品が揃うといよいよ組み立てです。組み立ての最終工程では部品が多くなるため、それぞれの部品の持つ小さなばらつきが大きな誤差になります。この誤差を解消するために、高い技術力を持った熟練の技術者がミクロン単位で調整する「精度出し」と呼ばれる工程を行い、精度を向上させます。
⑦運転調整
最終工程は時計が実際に正常に動くかの検査をします。動作確認後、精度確認をし、不備があれば 原因を究明し、再度修正を行います。
バンドの寿命も延ばせる!

ここまでは時計本体を長く使うための方法などを紹介しましたが、実はバンドも長く使うためのポイントがあります。先ほどオーバーホールの話の中で、汚れが部品の劣化を早めるとお伝えしましたが、バンドも金属のため汚れにより劣化が早まります。バンドの隙間に皮脂などが入り込み、固着する原因になります。汚れによりアジャストコマのピンが錆びたりする事で抜けてしまうことも。そうなると新しいピンやアジャストコマが必要になる場合があります。定期的にクリーニングをする事で汚れの固着を防ぎ、バンドの劣化も予防することができます。
まとめ
今回は時計の寿命についてと、大切な時計を長く使うためのポイントなどをご紹介しました。定期的なメンテナンスを行うことにより、時計の寿命を延ばすことが出来ます。ですが、オーバーホールや修理が必要な状態なのかを判断することは初めはなかなか難しいですよね。福井県で一番大きなショッピングセンターに入っているふくい宝石時計修理研究所では、様々な時計のオーバーホールの他修理もしているようですよ。是非一度相談してみてくださいね。

自分の持っているものや、人からもらったもの、今から新しく買おうとしている腕時計がどのくらい長持ちするのかというのは沢山の人が気になるところ。時計によって違ったメンテナンスが必要だということが分かりましたね!自分の時計がどのような状態なのか気になった時は近くの時計屋さんに相談してみるのがおススメですよ。
直通電話はこちらから!